 |  |
 |
| 松村: |
地方への移住は空き家問題に止まらないので、自治体でも対応する部署がはっきりしないんじゃないですか。
|
 |
| 嵩 : |
一番いいのは飯山市の「いいやま住んでみません課」や富山県南砺市の「南砺で暮らしません課」など、専門の課や係でワンストップの相談ができることですが、なかなか難しい。一番問題になるのが部署間で連携がとれておらずに相談者をたらい回しにしてしまうこと。またとにかく情報発信をすればいいと思ってしまう傾向はありますね。だけど移住前に必要な情報と移住後に必要な情報は違うので、一緒に発信してもわからなくなってしまう。
移住後のフォローは自治体では手が回らないので、受け入れる民間組織をつくってそちらで分担するのが大切です。一方、自治体から発信される情報は移住のきっかけづくりとして重要です。例えば朝日新聞がつくった「いつか住みたい都道府県ランキング」を見ると、上位は観光地を抱えているところばかりです。つまり、行ってみて良かったという体験が、住みたいと思うきっかけになっている。ですから、まずは行ってみたいと思わせる情報発信をしなければなりません。
|
 |
| 松村: |
そうした情報発信を上手く行っている自治体にはどんなところがありますか。
|
 |
| 嵩 : |
例えば長野県の飯山市は、民間も巻き込みながら行政主導で上手くやっている例だと思います。
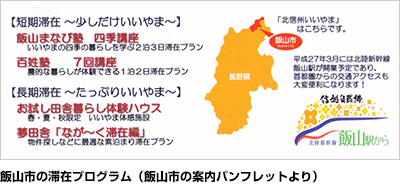
地域のことを知ってもらう短期滞在を「すこしだけいいやま」というキャッチフレーズで年四回募集しています。移住希望者は良い季節の体験だけで判断しがちです。これは移住失敗の元なので、自治体に対しても移住希望者に対しても、厳しい季節も体験して下さいとアドバイスしています。飯山市はそうしたきちんとした体験ツアーを十数年も企画しています。地元の観光協会ともしっかり連携できていて、「たっぷりいいやま」と呼ぶ長期滞在は民宿旅館で行っています。というのも、この地方の観光シーズンから外れるので、夏場は部屋が余っているんですね。
|