 |
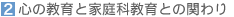 |
 |
| |
 |
(1)「人との関わりを意識して生活を創る」 (2)「『もっと○○したい。』意欲を引き出す学習環境を創る」2つの視点を大切にして家庭科学習を考えていくことにしたい。 |
 |
| |
|
(1)「人との関わりを意識して生活を創る」 |
| |
|
 |
子どもたちが家族を中心とした生活を創っていく上で、人の思いや気持ちを考え自分との関わりをどう工夫して生活に取り入れていくかを意識させた学習の場は必要であると感じる。また、人との関わりは家族だけではなく、生活を取り巻く地域社会の人々との関わりも大切に考えていく実践の場が必要である。人と関わることを通して自己実現することの楽しさや人のために役に立つことの満足感、自己肯定感を高めていきたいと思う。 |
 |
| |
|
(2)「『もっと○○したい。』意欲を引き出す学習環境を創る」 |
| |
|
|
生活課題を解決し自分の生活を改善し実践していく場は、家庭生活の場がほとんどであるが、ここでは、子どもたちの生活時間の1/3を占める学校生活の場を生活改善していくための実践の場としてとらえることにする。
子どもたちのより身近な生活課題を解決する場を設定し、学習したことを生かして生活を見直し工夫して改善していく体験の場とする。ここから再度、自分の家庭生活を振り返り、見直し生活改善していく実践的な態度「自分の生活をもっと工夫してよりよくしたい。」へとつなげたい。
|