原爆ドームに関する広島市のまちなみの問題
「原爆ドーム」は第二次世界大戦で被爆した建物を残すことで、後世への平和の願いが込められた建物です。現在では世界遺産に登録されており、私達が見にいった時は多くの国の人々がおとずれて、熱心に見入ったり、ガイドさんの説明に聞き入ったりしていました。
しかし、建物は外にそのままの状態で保存されているため、劣化を免れることは難しい状態です。劣化を防ぐための補強工事がなされ、安全のための囲いが設けられており、中に入って見学することはできません。
周辺にはある程度の広さが確保され、公園のようになっており、また前を流れる川沿いや護岸も緑化され、憩いのスペースとなっています。
 写真1 原爆ドーム外観
写真1 原爆ドーム外観
 写真2 対岸からみた様子。両サイドとも景観的な配慮がなされているのがわかる。
写真2 対岸からみた様子。両サイドとも景観的な配慮がなされているのがわかる。
 写真3 ビル群に埋もれる原爆ドーム。特に左側の建物は色も合わず問題となっている。
写真3 ビル群に埋もれる原爆ドーム。特に左側の建物は色も合わず問題となっている。
しかし、戦後の近代化により周辺には原爆ドームの高さを超えるビルが多く建設され、原爆ドームは川の反対側から見たときには、それらの建物に埋もれたようになっています。
私達は川沿いに原爆ドームに向かって左側からアクセスしましたが、かなり近くになるまで、原爆ドームを確認することはできませんでした。
平和のシンボルとしては、このような状態は問題です。しかし、既に建てられてしまった建物をつぶしたり、移動したりすることは難しく、現状では新たに建てる建物にのみ高さの規制をかけている状態です。
これは何も原爆ドームに限った問題ではなく、例えば東京大学の安田講堂、東京駅など歴史的建造物の周辺にも高い建物が建てられ、重要な意味を持つ建物が埋もれて目立たなくなっているという状況は今日では多々みられます。また関東付近では富士山の眺望を巡って問題が起きることも少なくありません。
このような状況を今後生み出してしまわないためには、どのような規制が有効でしょうか?以下の図1を見て下さい。
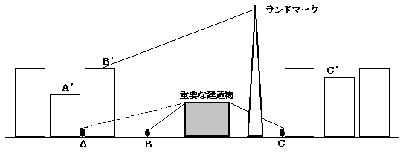 図1
図1
地点Aからは前のビルが邪魔となって重要な建造物は見えません。地点Bでは見ることができます。地点Cは重要な建造物が見える境目の地点です。建造物を外から見ようとした場合、このようにその地点と建造物の間に線を結ぶことによって知ることができます。この「見える」エリアを設定し、その間には建物は建てないという規制が一つ考えられます。
原爆ドームとは関係ありませんが、ランドマーク的な建造物、例えば東京タワー、各地にある五重塔、ランドマークとなるビルに関しても同じような手法が適用できます。例えば図のようなランドマークがあった場合。地点A'からは隣のビルが邪魔となってランドマークの一番上の部分さえ見えません。地点B'からは容易に見ることができます。地点C'からはかろうじて一番上の部分だけ見えます。この考えを適用すると、周辺の建造物の高さを規制することができます。
ここで説明したのは高さの問題だけですが、対岸からみた場合のその他の配慮(色彩など)も必要でしょう。
経済性を重視するあまり、私達は重要なものを忘れてきたような気がします。残すべき古きものと、そうでないものをはっきりと区別し、残すべきものには特別な配慮をすることが、後世に想いを、伝統を伝えることになるでしょう。
(文責:中田早耶)

まちなみ探訪
>> HOME
 写真2 対岸からみた様子。両サイドとも景観的な配慮がなされているのがわかる。
写真2 対岸からみた様子。両サイドとも景観的な配慮がなされているのがわかる。
 写真3 ビル群に埋もれる原爆ドーム。特に左側の建物は色も合わず問題となっている。
写真3 ビル群に埋もれる原爆ドーム。特に左側の建物は色も合わず問題となっている。
しかし、戦後の近代化により周辺には原爆ドームの高さを超えるビルが多く建設され、原爆ドームは川の反対側から見たときには、それらの建物に埋もれたようになっています。 私達は川沿いに原爆ドームに向かって左側からアクセスしましたが、かなり近くになるまで、原爆ドームを確認することはできませんでした。
平和のシンボルとしては、このような状態は問題です。しかし、既に建てられてしまった建物をつぶしたり、移動したりすることは難しく、現状では新たに建てる建物にのみ高さの規制をかけている状態です。
これは何も原爆ドームに限った問題ではなく、例えば東京大学の安田講堂、東京駅など歴史的建造物の周辺にも高い建物が建てられ、重要な意味を持つ建物が埋もれて目立たなくなっているという状況は今日では多々みられます。また関東付近では富士山の眺望を巡って問題が起きることも少なくありません。
このような状況を今後生み出してしまわないためには、どのような規制が有効でしょうか?以下の図1を見て下さい。
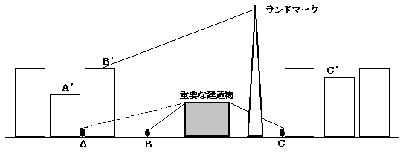 図1
図1
地点Aからは前のビルが邪魔となって重要な建造物は見えません。地点Bでは見ることができます。地点Cは重要な建造物が見える境目の地点です。建造物を外から見ようとした場合、このようにその地点と建造物の間に線を結ぶことによって知ることができます。この「見える」エリアを設定し、その間には建物は建てないという規制が一つ考えられます。
原爆ドームとは関係ありませんが、ランドマーク的な建造物、例えば東京タワー、各地にある五重塔、ランドマークとなるビルに関しても同じような手法が適用できます。例えば図のようなランドマークがあった場合。地点A'からは隣のビルが邪魔となってランドマークの一番上の部分さえ見えません。地点B'からは容易に見ることができます。地点C'からはかろうじて一番上の部分だけ見えます。この考えを適用すると、周辺の建造物の高さを規制することができます。
ここで説明したのは高さの問題だけですが、対岸からみた場合のその他の配慮(色彩など)も必要でしょう。
経済性を重視するあまり、私達は重要なものを忘れてきたような気がします。残すべき古きものと、そうでないものをはっきりと区別し、残すべきものには特別な配慮をすることが、後世に想いを、伝統を伝えることになるでしょう。
(文責:中田早耶)
