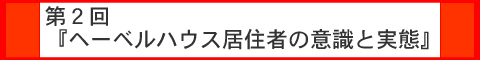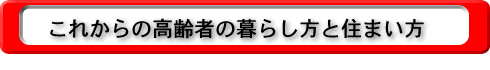 |
|
第1回に引き続き、新たな高齢者マーケットの住宅ニーズを探るため、20年以上前から「二世帯同居型住宅」をはじめとして、高齢期の住み替え支援の仕組みなど様々な提案を行ってきた旭化成ホームズの取り組みについて、同社・住宅マーケティング総部の松本氏、入澤氏を講師に招き講義をして頂いた。 |
||||
| ■主 催 | ||||
| 高齢社会研究会 |
 |
|||
| ■日 時 | ||||
平成16年9月24日(金) |
||||
| 18時00分〜20時30分 | ||||
| ■会 場 | ||||
住宅生産団体連合会 会議室
|
||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |
||||||
|
||||||
| ◆旭化成の二世帯住宅・高齢者配慮対応の歴史 | ||||||
| 1.二世帯住宅を提案した時代 1975年、二世帯住宅を商品化し、一つ屋根の下に2つの家族が住むことを提案した。旭化成の二世帯住宅のコンセプトは「Nice Separation(暮らしを分けると気持ちがくっつく)」。実際の生活面でも、相手世帯の生活を尊重するという意識面でも、日常生活を分けることによって両世帯の良好な関係維持と同居のメリットを最大限享受する基盤となる、というものであった。2つの家族をどう分けるか、分けるためのハード開発(外階段+2階玄関、ALC床遮音、1・2階独立で自由な間取りが可能な構造など)が行われた。 |
||||||
| 2.二世帯住宅が普及した時代 バブル期において土地が高騰し都市近郊に家を取得することが難しくなった。 その時代の選択肢は大きく2つに分けられた。1つは郊外の住宅を購入する。もう一つは、親が都内に住んでいる場合、二世帯住宅を建ててそこに同居する。 後者の場合は相続税対策としての意味も持っていた。二世帯住宅が普及するに伴い様々な居住者ニーズが明らかになり、同居のための計画ノウハウを整理する必要が出てきた。その結果として、1987年に息子夫婦同居型:DUO、娘夫婦同居型:DUETが提案された。当時は女性が家事をすることが前提とされており、同じ家で同居する女性2人が他人かどうか、それが住宅プランに影響を与えている。 その後の1993年には、親世帯≒高齢者であり、かつ全ての人が高齢者となるという考えで、長寿社会対応を標準化し全ての住宅に適用、1998年にはユニバーサルデザインを志向したロングライフ設計・ロングライフ住宅を基本戦略とした取り組みを実施してきた。 |
||||||
| ◆20年を超えた二世帯住宅の居住者の実態と意識 | ||||||
| 20年前に二世帯住宅を購入した世帯の1/3は核家族化しており、既に二世帯住宅ではなくなっている。 将来の生活については、できるだけ長く住み続けたいと考えている世帯が多いが、当初の子供世帯が自分の子供と2世帯住宅として使っていきたいと積極的に考えている人はあまり多くない。 居住者の感想として、自分や家族が急病の時に心強いなどの「安心」、伝統的あるいは新しい文化・習慣についての「学習」、子供の世話などの「子育て支援」などが良かった点としてあげられ、「干渉」や「家族関係への気遣い」が不満としてあげられている。傾向として面白いのは全部裏腹であること。基本的にセパレーションがきちんとできていて好きなときに何らかの関係が持てる方が良いという事がわかる。安心・サポートといったメリットは入居時には子世帯の方が感じているが、これが10年も経つと逆転する。 今後のロングライフ住宅の方向性としては、家族同居によって得られるメリット、すなわち私的価値だけではなく、高い社会的価値(売買+収益価値)を備えたものとして展開していくことが必要。 |
||||||
| ◆高齢期に自宅を売却して住み替えた人の状況−ストックヘーベルハウス利用を含めた住み替え者調査結果より− | ||||||
| ヘーベルハウス以外の住宅では、30代での購入、40代での売却が多くなっているが、へーベルハウスでは40代購入、50代売却の割合が多い。へーベルハウスの売却のきっかけとしては、転職・転勤・退職、子供の成長などの生活変化が大きな理由となっている。介護の必要性が生じたためという理由はヘーベルハウスの方が他の住宅より高くなっている。 ヘーベルハウス売却者が売却住宅に持っていた不満としては周辺環境、敷地面積の広さなどがあげられている。敷地面積の広さについては、高齢期を迎える住宅としては広すぎる、とはいえ2世帯住宅にするには狭いということではないかと分析している。 今後、良質なストックを数多く市場に出すためには、購入者の意識の醸成(中古住宅だからといって妥協しない意識・価値観)、建物価格の明示(土地・建物の価格を分けての売却価格の決定)、建物情報の開示(購入者の安心、満足のために適切な情報伝達)、サポート態勢の充実(安心して住み続けられるための「家守」的機能充実)が重要であると言える。 |
||||||
| ◆所有したまま賃貸にして住み替える仕組み(リムーブ) | ||||||
高齢期の住み替えの問題は、まとまった資金がいることである。一般的には、家を売って対処することが多いが「戻れない不安」を伴う。それに対して、旭化成は家を貸して住み替えるスキーム、−即ち、所有したまま貸して賃貸収入を得て住み替えるしくみ−を開発した。その際、追加で資金が必要な場合は、月々は利息のみの返済で、その家の査定内での融資を行い、死亡時に精算するしくみも合わせもっている。
|
||||||
 |
||
第1部の講演に基づき、二世帯住宅の世帯構成の変化と使われ方、高齢期の生活変化と住宅性能、住み替えの動機、志向などについての質疑が行われた。 |
||
| 1.現在の高齢化を背景に二世帯住宅が増えてきているのではないかとも思うが、その傾向はいかがなものか? | ||
| 二世帯住宅のシェアが高齢化の進展により増大していることはないと思う。 | ||
| 2.二世帯住宅の世帯構成として、息子夫婦同居と娘夫婦同居の増減の傾向と、その理由は? | ||
| 娘夫婦との同居が微増し、息子夫婦同居が減少した結果である。息子夫婦同居が減少した理由としては、母親とお嫁さん、両世帯で女性が嫌がることがあげられる。 | ||
| 3.3分の1は二世帯同居ではなくなっているとのことであるが、そのプロセスは? 両親が共に亡くなる前に二世帯住宅ではどのような事が起きているのか? | ||
| ヘーベルハウスの居住者においても世の中の平均と同じように男性の方が早く亡くなっている。形態として「子世帯4人+母親」か、子(孫)の独立が早ければ「子世帯夫婦2人+母親」という世帯数が増えている。高齢者がいるのに子世帯が出て行ってしまい二世帯住宅に母親が単身という形態もほとんどない。 | ||
| 4.二世帯住宅はパラサイトを生み出しやすいということはないか? 例えばおじいちゃん、おばあちゃんの所が空いてしまうから結婚しなくても居場所があるとか。 | ||
二世帯住宅をつくるときは親世帯と子世帯のスペースが1対1程度でつくる。子世帯は概ね4人家族、親世帯は2人なので親世帯の方に余裕がある。実態はつかんでいないが、子世帯のスペースが狭いときその子供(孫)がどのように親世帯を侵食していくのか、その家族生活への影響は面白いテーマだと思う。 |
||
| 5.ストックへーベルハウスの売却の理由として「介護」事由の数字が他の住宅と比較して高いように見える。その理由をどう考えているか? | ||
| 介護経験が「ある」の人に着目し、それを同居継続者と同居中断者で分けたところ、同居中断者の方が多い。長寿社会対応を標準化する前の時代のものであり、ハード的に介護を長期間続けられるかどうかの問題もあったと思う。また、「気兼ねのある他人の嫁に長期間の介護」ということも考えると、まだまだハードとして考えることがありそうである。 | ||
| 6.「住替え時のこだわり」についてのアンケート結果が、へーベルハウスとそれ以外でかなり違うという印象。理由はどのように考えているのか? | ||
| 今回の調査結果は、対象者である高齢期世代をひとくくりにして違いを見ているが、65歳以上の居住者では、再度戸建に住み替えている世帯が半数であったり、50代(団塊世代)は都心マンションに住み替え、都会ライフをエンジョイしたいというニーズが見えたり、一概には言い切れないのが事実である。 更に細かく見ていく必要があると思っている。 | ||
| 調査結果としては分析しきれていないが、これまでの経験から申し上げると、世田谷・杉並で住替えたいと言っている層は、土地のポテンシャルや地域文化の良さは充分認識し、長年かけて自分達のコミュニティーを形成しているので、その生活圏の中で、夫婦ふたり超高齢期でもより利便・快適・安全な環境を得ることが前提となっていると考えられる。 ただ、事例があまりないだけにイメージが定まらないのが現状で、具体的な住み替えのプラン提案(選択肢)が求められていると思われる。 | ||